問題
次の文章を読んで、設問に答えなさい。
事実
納税者Aは、昨年12月に2,500万円の現金を父親から贈与された。
翌年3月15日の直前の日に、相続時選択課税選択届出書と法令に規定の添付書類全て、また、当該制度適用開始年度(前年度)分の贈与税申告書を提出した。
ところが、その贈与税申告書は、相続時精算課税欄のある第二表を提出せず、誤って暦年課税欄の第一表のみに「年分」「贈与額」「税額」などの必要事項を記入し、提出していた。
申告期限後にこの事実に気づいた税務署Bは、第二表を提出していないが故に相続時精算課税制度の特別控除である2,500万円は使えないが、かといって相続税法第21条の9第6項に基づき相続時精算課税制度の撤回も許されないため、対応に困った。
そこで税務署Bは、相続時精算課税制度に基づく今後の贈与は、期限内申告であれば認めるが、今回の贈与については、2,500万円の特別控除枠も使えないし、暦年課税制度上の特例税率も使えない。すなわち、本来は同制度の適用者向けの税率である一律20%課税を課すとの方針を固め、署の贈与税担当者を通じて、その旨の行政指導を行なった。
これに対して納税者Aは、「それはおかしい。取下書を出すから第二表を再提出させてくれ。それに、一律20%課税のせいで、本税が増えるではないか」と怒りながら応答したが、税務署Bは「相続税法において期限内申告であることが定められているから、再提出は難しい。早く本税を支払わないと、延滞税が増えていく恐れがある。」と述べるにとどまった。
何日か押し問答の末、納税者Aは延滞税の存在が怖くなり、渋々不足分の本税を納め、その後、延滞税も完納した。
設問
税務署Bの課税の判断は正しかったのか、租税法の観点から結論しなさい。
解答例
1 税務署Bによる課税の判断が正しかったのかどうかについては、相続税法(以下「法」という。)の法律解釈が適切であったのか、また、租税法律主義(憲法第84条)に基づく行政上の判断であったのかどうかが問われることとなる。
2 思うに、相続時精算課税制度(以下「同制度」という。)の不適用の根拠とした相続税法第21条の12第2項(以下「同条」という。)においては、記述事項の指定はあるものの、贈与税申告書第二表そのものを提出しなければならない旨の明文化はなされていない。
また、他の条文においても、同条が第二表の提出を前提とする条文であるとの記述もない。
すなわち、文理解釈によれば、この納税者Aは同条に規定の事由を第一表に記載しているのだから、同条にいう相続時精算課税制度の適用要件を満たしているといえる。
3 これに対して、同条の事由は第二表に記載する前提であるといえるのだから、第二表の提出がなければ同制度が不適用となることは当然の理であるとする見解もある。
たしかに、実務的な観点から趣旨解釈をすればそのような結論に至ることも考えられる。
けだし、文理解釈と趣旨解釈が相反した場合は、原則として文理解釈が優先される上、本件において文理解釈を否定すべき特段の事由も見当たらない。
だとすれば、文理解釈を検討せずにいきなり目的論的解釈の一種である趣旨解釈に走るのは、法の解釈手順を誤っているというべきである。
4 加えて、同制度の不適用の論を採用した場合、特別控除適用時の一律20%課税という課税制度を特別控除不適用者にも適用するという、法の意図に反した税制の運用を行うこととなる。
これでは法が予定していた法意に違背することとなり、本来の立法趣旨と異なることから、妥当な結論とは到底いえない。
5 また、「一律20%の課税を同制度の特別控除不適用者にも適用してもよい」とする法律の規定でもない限り、成文法化された課税要件なしに租税を課税することは租税法律主義の観点から許されないことであって、法律の定めなしに国民は納税の義務を負わない(憲法第30条)のであるから、税務署Bの判断は違憲無効であるとの謗りを免れることができない。
6 そうすると、税務署Bの判断は、畢竟独自の見解にすぎないのだから、法律解釈及び租税法律主義の観点から、違憲性を帯びた行政指導であり、当該課税の判断は誤ったものであるといえる。
以上
※注意
このWEBページに記載の内容は、筆者の独自意見である。
納税者は必ず租税に通じた弁護士または税理士もしくは税務署に相談し、税務の実務家(税理士や税務職員)においては、自身のリーガルマインドにより法論理的に適切な結論を導くことに、くれぐれもご留意いただきたい。
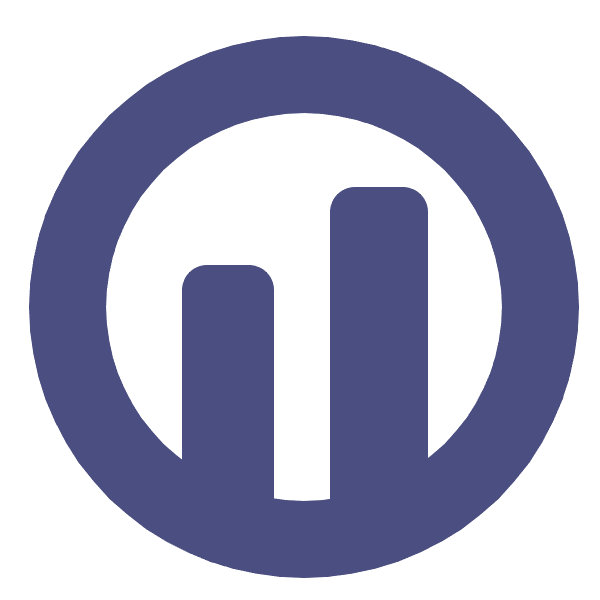 THE BUSINESS TIMES
THE BUSINESS TIMES