財産の意義
相続税法第11条又は第11条の2において、相続又は遺贈により財産を取得した者の課税関係を規定しているが、ここでいう「財産」とは何を指すのか。
相続税法基本通達11の2-1によると、「法に規定する「財産」とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいう」と観念されている。
なるほどたしかに、経済的価値のあるすべてのものが対象であると法が予定しているように考えなければ、課税の抜け穴ができてしまう。
したがって、物権や債権、無体財産権に限らず、営業権のような経済的価値があるものも含まれると解される。
贈与財産の加算
特定贈与者たる被相続人からの相続時精算課税制度を用いた贈与については、相続税の課税価格に算入するが、相続開始年においては贈与税の課税価格にも算入される。
また、暦年課税に係る贈与については、法の改正前は相続開始前3年以内であったが、改正後は相続開始前7年となり、現在段階的に移行している(相続税法第19条)。
| ケース | 相続税の課税価格への算入 | 贈与税の課税価格への算入 |
| 相続開始年以前の相続時精算課税による贈与 | 要する | 申告済みであれば不要 |
| 相続開始年における相続時精算課税による贈与 | 要する | 要する |
| 相続開始年前7年以前の暦年課税による贈与 | 不要 | 不要 |
| 相続開始年前7年内の暦年課税による贈与 | 要する(※段階的移行中) | 不要(※段階的移行中) |
事例検討:胎児と相続税申告
民法第3条第1項において「私権の享有は、出生に始まる。」と定められており、胎児は生きて生まれれば自然人としての権利能力を有するようになると考えられている。
また、民法886条では、相続において胎児はすでに生まれたものとみなされている(出生擬制)。
では、相続人の中に胎児がおり、相続税申告時期において産まれるのか産まれないのか定かでない場合、実務上どのような取扱いとなるのか。
この点につき、相続税法基本通達11の2-3においては、相続税の申告書提出の時において無事に産まれていれば法定相続人に含め申告し、死産若しくは産まれていない場合はその胎児がいないものとして法定相続人の数に算入せずに課税価格を計算することとなる。
この場合、相続税の申告書提出後に相続人たる胎児が生きて出産したら、修正申告又は更正の請求をすることとなる。
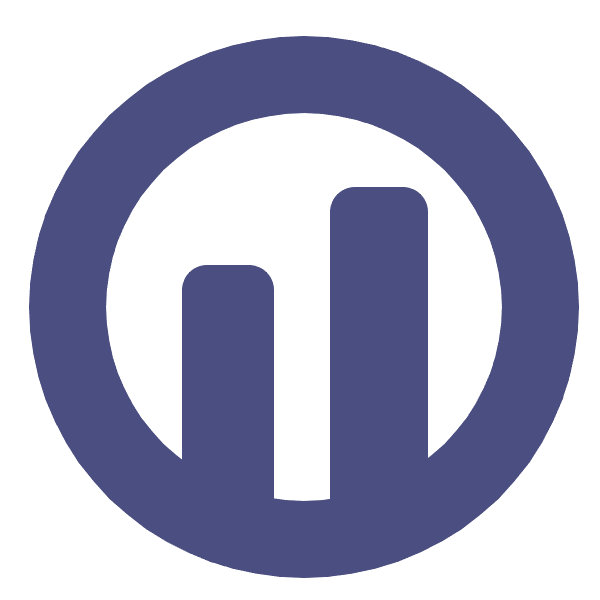 THE BUSINESS TIMES
THE BUSINESS TIMES