還付金請求
いわゆる還付申告というもので、払いすぎた所得税が戻ってくる国税の申告手続きです。
還付申告による還付金請求は、その請求をすることができる日から5年間はできます。※1
ここでいう「その請求をすることができる日」とは、その申告年分の翌年1月1日を指します。
還付申告は納税を要する申告とは違い、翌年1月1日からできますからね。
例えば、令和7年(2025年)中に還付金請求ができるのは、以下の年度分の所得税です。
- 令和6年(2024年)分:令和11年(2029年)12月31日まで有効
- 令和5年(2023年)分:令和10年(2028年)12月31日まで有効
- 令和4年(2022年)分:令和9年(2027年)12月31日まで有効
- 令和3年(2021年)分:令和8年(2026年)12月31日まで有効
- 令和2年(2020年)分:令和7年(2025年)12月31日まで有効
令和元年(2019年)以前の所得税の還付金請求はできませんので、ご注意ください。
なお、一度申告し、申告期限が過ぎている場合は、還付金のための「期限後申告」ではなく、「更正の請求」になりますから注意してください。
※1 国税通則法第74条第1項
更正の請求
更正の請求とは、一度申告したが計算誤りなどを発見し、再計算をしたら結果的に税金を払いすぎていたので「返してほしい」と請求する手続きです。
更正の請求は3つのケースがあり、それぞれに起算点や消滅時効の期日が定められています。
(1)計算誤りの場合
よくある「計算の誤り」による理由です。
この場合は、法定申告期限から5年間は、請求できます。※2
例えば、所得税なら以下のとおりです。
- 令和6年(2024年)分:令和12年(2030年)3月15日まで有効
- 令和5年(2023年)分:令和11年(2029年)3月15日まで有効
- 令和4年(2022年)分:令和10年(2028年)3月15日まで有効
- 令和3年(2021年)分:令和9年(2027年)3月15日まで有効
- 令和2年(2020年)分:令和8年(2026年)3月15日まで有効
- 令和1年(2019年)分:令和7年(2025年)3月15日まで有効
ただし、所得税法第122条の例外がありますので、注意してください。
※2 国税通則法第23条第1項第1号
(2)法律行為の基礎に誤りがあった場合
法律行為の基礎に誤りがあった場合とは、計算の前提となる事由に法的な間違いがあり、最初から税額の計算をやり直したい場合です。
例えば、皆さんが税金を納めるのは、何かしらの法律行為を行ったからです。
物を売った場合(民法でいう売買契約)は、所得税の事業所得や法人税。
誰かから贈与を受けた場合(民法でいう贈与契約)は、贈与税。
亡くなった人から財産を得た場合(民法でいう相続または遺贈)は、相続税。
「税金を納める=前提となる法律行為を行った」ということなのです。
では、もしその前提が、裁判や和解などで崩れたら?
話が全然変わりますよね?
そういったケースを想定しているのが「法律行為の基礎に誤りがあった場合」なのです。
話が長くなりましたが、この場合は、判決や和解などの確定した日の翌日から起算して二月(2か月)以内であれば、請求できます。※3
逆に言うと、2か月以上経ってしまったら、更正の請求はできなくなります。
「更正の請求といえば5年間有効!」と安易に仰る方がいますが、全てのケースではないのでご注意ください。
※3 国税通則法第23条第2項第1号
(3)政令で定めるやむを得ない理由による場合
上記2つのケースに当てはまらなかった方。
まだ諦めないでください。
国税通則法施行令第6条第1項に列挙された事由に当てはまれば、まだチャンスがあります。
その事由とは以下のとおりです。
- 計算の基礎になっていた官公署の許可その他の処分が取り消されたこと
- 解除権の行使により契約が取り消されたこと
- 帳簿書類の押収等で計算ができなくなり、その後、当該事情が消滅したこと
- 法令もしくは通達が、裁判や裁決で否定され、その後、改正等で法令解釈の変更が発表されたこと
上記のケースに当てはまる場合は、当該事由が生じた日の翌日から起算して二月(2か月)以内に請求してください。※4
なお、3つのケースのいずれにおいても、請求の理由となる事実を証明する書類を添付する必要がありますので、申し添えます。※5
※4 国税通則法第23条第2項第3号
※5 国税通則法施行令第6条第2項
附帯税
附帯税とは、延滞税や加算税といった行政上のペナルティによる税金の総称です。
時効により消滅する時期は以下のとおりです。
- 延滞税:各税金の法定納期限から5年で時効により消滅
- 加算税:〃
消滅時効は上記のとおり※6ですが、実務上は5年で済まないでしょう。
なぜならば、あなたが納税の猶予や延納といった税金を先延ばしにする制度の利用中は時効の進行が止まっていますし、他にも時効の進行がストップする期間の定めがあります。
現実的には、あまり軽々しく「税金から逃げよう」などとは思わないほうが良いでしょう。
※6 国税通則法第72条第1項
プロパティ
カテゴリー
関連タグ
その他
作成日:
更新日:
投稿者:管理人
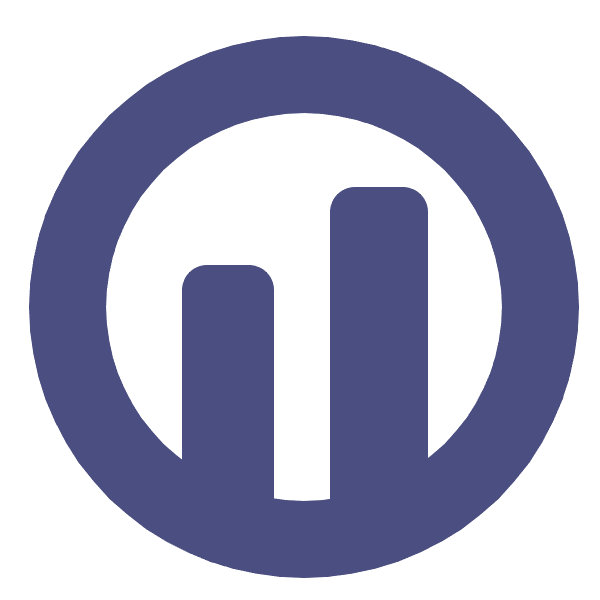 ビジネス法務事務所
ビジネス法務事務所