相続税の財産の中でも、課税されない財産がある。
これを「相続税の非課税財産」といい、具体的には以下のとおりである。
皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物(同条第1項第1号)
三種の神器などの皇室固有の承継財産は、一般的な相続財産として課税対象とすることは相応しくないため、非課税財産として除外されている。
墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの(同条同項第2号)
民法第896条の例外である同法第897条第1項本文においては、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と規定している。
この規定から相続税法上も、墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものは、非課税財産としている。
なお、同号にいう「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神だな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであって、「商品、骨とう品又は投資の対象として所有するもの」はこれに含まれない(相続税法基本通達12-2)。
したがって、資産価値のある金の仏像や金の仏具などは、商品であり、投資の対象としてみなされる可能性がある。
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの(同条同項第3号、相続税法施行令第2条)
個人又は人格のない社団等が行う宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業については、それら事業用財産を非課税財産とする規定である。
適用対象者の範囲については、相続税法施行令第2条を参照されたい。
また、通達においては、公益事業用財産について「個人の生活の用に供されるもの」や「公益事業を行わないとき」、「2年以内に公益事業を行うときであっても、当該事業の用に供していないとき」は、これに該当しないことが重ねて明記されている(相続税法基本通達12-3、12-4)。
条例の規定による心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権(同条同項第4号、相続税法施行令第2条の2)
心身障害者扶養共済制度により支給されている給付金については、所得税法上、非課税となっている(所得税法第9条第1項第3号ハ)。
そのため、相続税法上も非課税財産としている。
なお、ここでいう「政令で定める共済制度」とは、所得税法施行令第20条第2項に規定する共済制度をいう(相続税法施行令第2条の2)。
相続人が相続により取得したものとみなされる生命保険金等の合計金額のうちの一定額(同条同項第5号)
生命保険金等などでその合計額のうち一定金額は、相続税がかからない。
ここでいう一定金額は、「500万円×法定相続人の数」をいう。
なお、相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金額については、この適用はない(相続税法基本通達12-8)。
相続人が相続により取得したものとみなされる退職手当金等の合計金額のうちの一定額(同条同項第6号)
退職手当金等についても、先述の生命保険金等と同様の規定となる。
国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税(租税特別措置法第70条)
相続又は遺贈により財産を取得した後であっても、財産を取得した相続人又は受遺者がその財産を国、地方公共団体、特定の公共法人等、特定公益信託又はNPO法人に贈与・寄付した場合には、その贈与によりその相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときを除き、その贈与した財産の価格は、その相続又は遺贈にかかる相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされている。
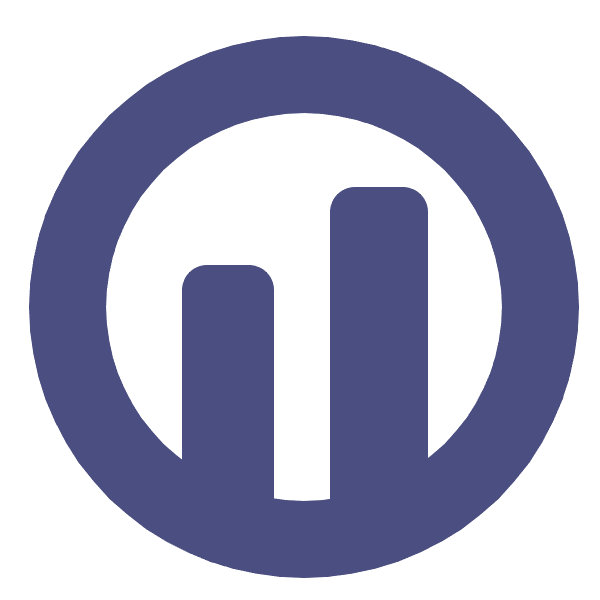 THE BUSINESS TIMES
THE BUSINESS TIMES