第1条の3:相続税法上の納税義務者
同条の納税義務者をまとめると、以下のとおりである。
- 居住無制限納税義務者(相続税法第1条の3第1項第1号)
- 非居住無制限納税義務者(相続税法第1条の3第1項第2号)
- 居住制限納税義務者(相続税法第1条の3第1項第3号)
- 非居住制限納税義務者(相続税法第1条の3第1項第4号)
- 相続時精算課税の適用選択者(相続税法第1条の3第1項第5号)
意義
まず、同条で規定されている用語の定義を確認したい。
個人
ここでいう個人とは「自然人」を指す(相続税法基本通達1の3・1の4共-1)のであり、法人は含まれない。
民法において相続権は一身専属権であるから、言うまでもないことである。
ただし、みなし贈与・みなし遺贈により、法人であっても個人とみなされ、実務上、課税対象とされる可能性がある(相続税法第9条の4第3項、相続税法第66条、相続税法第66条の2、相続税法基本通達1の3・1の4共-2)。
住所:複数の居所がある場合の住所
ここでいう『住所とは各人の生活の本拠をいう』のであると、相続税法基本通達1の3・1の4共-5に記述されている。
これは、民法第22条の『各人の生活の本拠をその者の住所とする。』という規定の確認である。
また同通達においては、『同一人について同時に法施行地に二箇所以上の住所はないものとする。』としている。
これは現行民法が「住所は単一である」という単一説を採用しているということへの確認である。
武富士事件(最判平23・2・18判時2111・3)においても『ここにいう住所とは、反対の解釈をすべき特段の事由はない以上、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所である』と判示されている。
論点:二重国籍者は納税義務者か
次に、同法同条において問題とされがちな論点に触れたい。
同条においては、「日本国籍を有する者」あるいは「有さない者」といった概念が出てくるが、日本国籍と外国国籍を有する二重国籍者(重国籍者)である場合は、どのように考えればよいのか。
この点について、法の適用に関する通則法第38条第1項ただし書において、当事者が二以上の国籍を有する場合、『その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。』と定められており、日本国の法律が適用される。
現に相続税法基本通達相続税法基本通達1の3・1の4共-7においても、同様の趣旨で法の解釈基準が確認されている。
第2条:相続税の課税財産の範囲
第2条においては、第1条の3において分類された納税者に応じて、課税財産の範囲を指定している。
無制限納税義務者については、財産の全部(第2条第1項)に対して課税される。
制限納税義務者については、この法律の施行地にあるもの(第2条第2項)に対して課税される。
第2条第2項の「この法律の施行地」は、無論「日本国内」を指すが、各種の財産の種類に応じては論点が生じうる。
この点については、第10条「財産の所在」の項に譲る。
プロパティ
カテゴリー
関連タグ
その他
作成日:
更新日:
投稿者:管理人
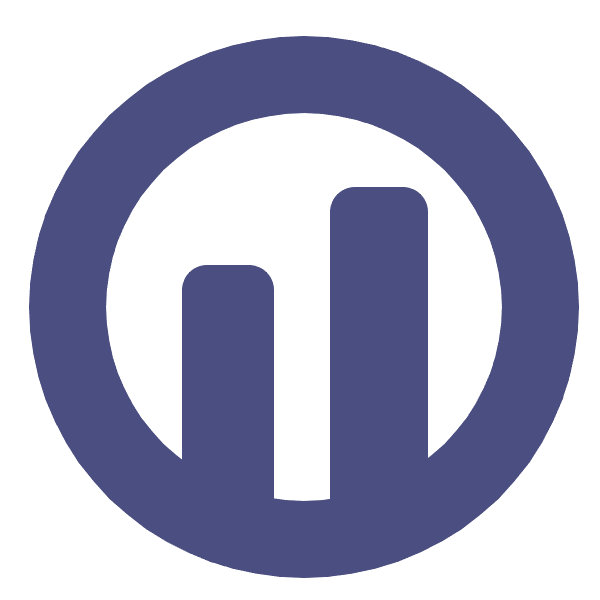 ビジネス法務事務所
ビジネス法務事務所