条理
相続税法第2条及び第2条の2において、相続税及び贈与税の課税財産の範囲が示された。
特に、第2条第2項及び第2条の2第2項においては、「その法律の施行地にあるもの」と指定されており、日本国内の財産であるかどうかの判定が求められる。
そこで第10条において、財産の所在の判定を行うことになる(相続税法基本通達2・2の2共‐1に同旨)。
具体例
例えば、動きようのない不動産や金融機関の営業所などは言うまでもないが、動産や貸付金債権などの場合はどうか。
動産については、同条第1項第1号において「動産の所在」とされ、相続の開始の時(相続税法基本通達1の3・1の4共‐8(1))または契約の効力発生日あるいは履行の時(相続税法基本通達1の3・1の4共‐8(2))における動産の所在により判断される。
貸付金債権については、同条第1項第7号において「その債務者の住所」とされ、債務者の住所が日本国内であるならば、課税対象の財産となる。
ただし、貸付金債権については、事業取引に関して発生した債権は含まれず(相続税法基本通達10-3)、また債務者が二以上ある債権については、主たる債務者の住所(相続税法第10条第1項第7号かっこ書き)であり、主たる債務者がいないときは、日本国内の債務者がいるときはその者、いないときは当該債務者の住所地となる(相続税法施行令第1条の14)。
プロパティ
カテゴリー
関連タグ
その他
作成日:
更新日:
投稿者:管理人
前後の記事
- (前)相続税法第1条の3・第2条
- (次)相続税法第3条
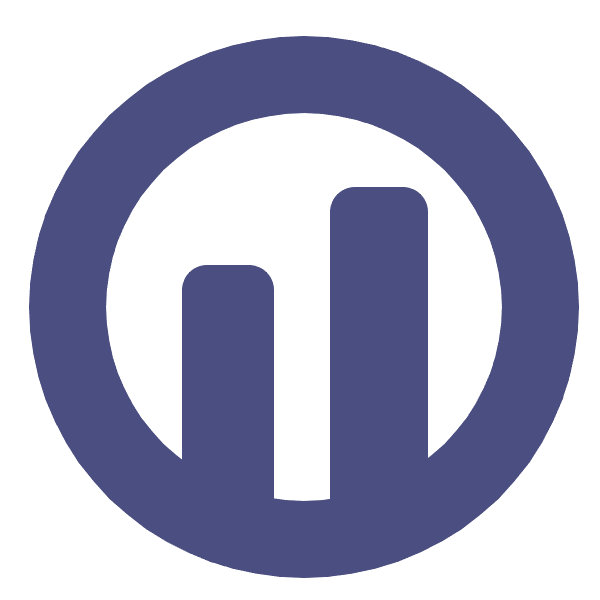 ビジネス法務事務所
ビジネス法務事務所