法の趣旨
ある者が、被相続人の死亡により利益を得たとしても、その財産が相続開始時に被相続人あるいは遺贈者に帰属していなければ、民法上、相続財産になり得ない(民法第896条)。
しかし、死亡による生命保険金の受け取りや権利については、被相続人の死亡により財産を取得することに相違なく、相続や遺贈のようにも見える。
そこで法は、当該みなし相続財産を相続人が受け取ったときは相続とし、それ以外の者が受け取ったときは遺贈とすることにより、税の公平負担を図ろうと考えた。
みなし課税の規定がなければ、生命保険金等を用いた相続税負担の抜け道ができることにより、税の公平性を担保できないためだ。
みなし相続財産の種類
同条においては、以下のものを相続財産とみなしている。
- 生命保険金(相続税法第3条第1項第1号)
- 退職手当金(相続税法第3条第1項第2号)
- 生命保険契約に関する権利(相続税法第3条第1項第3号)
- 定期金に関する権利(相続税法第3条第1項第4号)
- 保証期間付定期金に関する権利(相続税法第3条第1項第5号)
- 契約に基づかない定期金に関する権利(相続税法第3条第1項第6号)
そして、これらを取得した相続人あるいはそれ以外の者に対して、みなし相続ないし、みなし遺贈により課税関係が生じうることとなる。
ただし、相続人については、相続を放棄した者及び相続権を失った者は含まれない(相続税法第3条第1項かっこ書き)。
なお、ここでいう相続を放棄した者及び相続権を失った者については、実務上の注意点がある。
相続を放棄した者
相続の放棄は法定上、熟慮期間(民法第915条第1項、民法第916条、民法第917条)内に、家庭裁判所に申述(民法第938条)して初めて相続放棄をしたことになる。
相続税法は民法の概念を借用しているため、法律上の手続きを経なかった事実上の相続放棄をした者は、同条にいう相続を放棄した者に含まれず、課税関係が生じうる点に注意が必要である(相続税法基本通達3-1)。
相続権を失った者
相続権を失った者については、民法においていくつかの定めがある。
- 相続人の欠格事由(民法第891条各号)
- 推定相続人の廃除(民法第892条)
- 遺言による推定相続人の廃除(民法第893条)
これらの規定により相続権を失ったのでなければ、その者は同条にいう相続権を失った者に含まれないと解されるため、課税関係が生じうる(相続税法基本通達3-2)。
プロパティ
カテゴリー
関連タグ
その他
作成日:
更新日:
投稿者:管理人
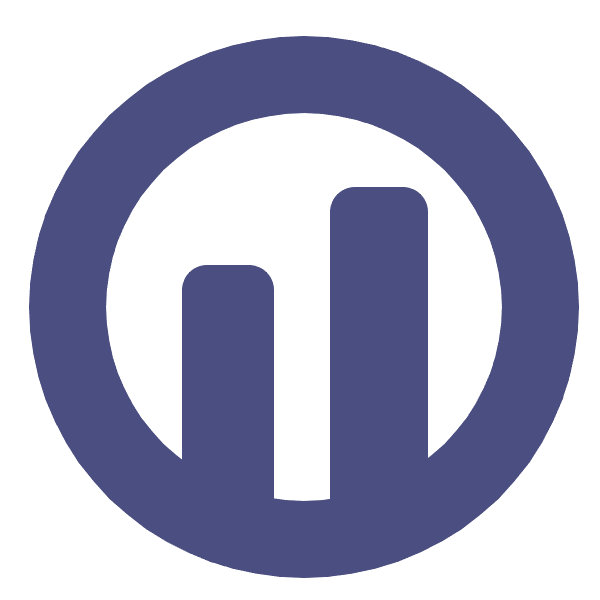 ビジネス法務事務所
ビジネス法務事務所