相続税又は贈与税の納税義務者のうち、制限納税義務者に係る課税財産は、相続税法の施行地(つまり日本国内)にある財産とされている(相続税法第2条第2項、第2条の2第2項)。
相続税法第10条では、この課税財産の所在の判定基準とされる場所を財産の種類ごとに定めている(相続税法第10条第1項第1号ないし第13号)。
なお、この課税財産の所在の判定は、当該財産を相続等又は贈与により取得したときの現況によるとされている(相続税法第10条第4項)。
事例検討:日本在住の父が海外在住の子へ国際電信送金したら?
結論は、日本の相続税法の規定に従って課税の判断がなされる。
相続税法第10条第1項第4号において、金融機関に対する預金・貯金については、その受入れをした営業所又は事業所の所在地によるとされているのだから、送金元の金融機関の所在地が日本国内になる以上、海外在住の子は、日本国内の財産を取得したと判断される。
また裁判例においても、「相続税法第10条が相続、遺贈又は贈与に因り取得したときの現況による規定している財産の取得時とは、契約締結時をいうものと解すべきであり、仮にそうでなくても日本国内の前記銀行において電信送金による送金手続きを了した時ということができる。」旨、判示している(東京高判平14・9・18判時1811・58)。
贈与契約時にも日本国内にあった預金が贈与対象になるし、送金時においても日本国内にあった預金が贈与対象となるのだから、どの道、国内金融機関から国外金融機関を介しての贈与は、日本国の相続税法が適用されるという結論となる。
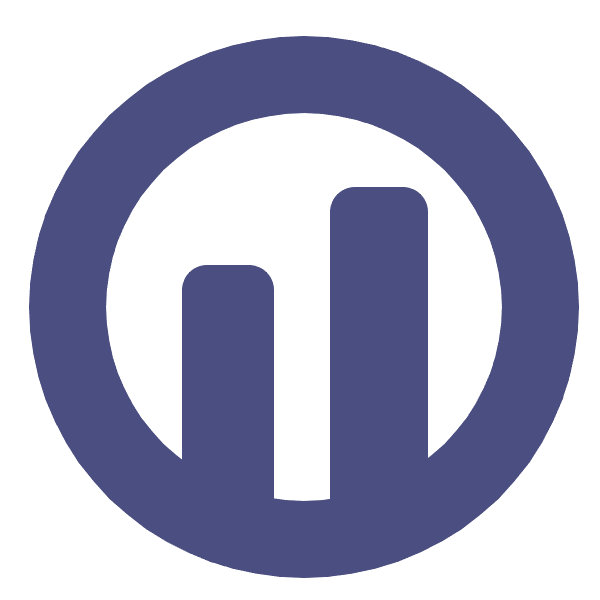 THE BUSINESS TIMES
THE BUSINESS TIMES